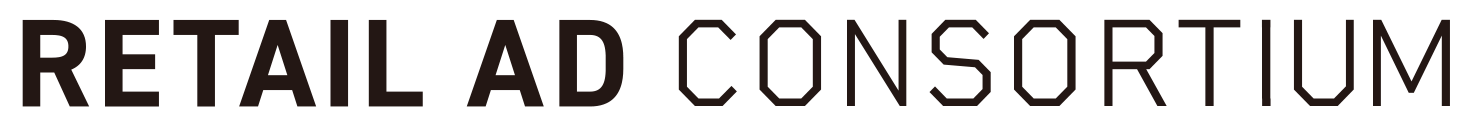topics
消費者への新たなアプローチ「感覚マーケティング」とは 外川拓・上智大学准教授に聞く㊦
7月20日に東京都内で開催した上智大学の外川拓・准教授による講演「感覚マーケティング ―五感訴求のコミュニケーション戦略―」。講演の後半では、様々な理論と組み合わせた感覚マーケティングの研究事例や、デジタルとアナログを組み合わせた取り組みにまで話題が及んだ。
<㊤はこちら>
◇
-1.jpg)
五感についての研究事例を紹介する外川准教授
◆香りは記憶を呼び覚ます
嗅覚をマーケティングにどう採り入れるかは、重要な問題だ。2015年に米経営学術誌「ハーバード・ビジネス・レビュー」に報告された韓国の市営バスの事例を紹介したい。車内でコーヒーの香りを漂わせ、ドーナツ店の広告を放送したところ、沿線のドーナツ店の売り上げが伸びた。ドーナツそのものではなく、コーヒーの香りという間接的なものでも実際の売り上げを押し上げたというのが興味深く、嗅覚の影響力の強さを示している。
米ラトガース大のM. モリン教授らが行った研究では、ショッピング・モールで、「柑橘(かんきつ)系の香り」と「ゆったりとした音楽」を、店内で流す実験を行ったところ、香りだけを流した時に、来店客の買い物に支出する金額が一番高くなった。香りと音楽の両方を流すと、支出額はかえって下がっていた。
モリン教授らは、この現象を「最適刺激水準理論」によって説明している。この理論によると、人には、心地よいと思う刺激の強さがあり、あまりに強い刺激を受けると、五感がさまざまなかたちで受ける「刺激水準」の総量を引き下げようとする。この実験でも、香りと音楽を両方に接した消費者は、刺激水準を抑えようとし、モール内で立ち寄る店舗の数、手に取る商品の数などを減少させたのだと考えられる。感覚的な訴求を行う際にも、適切なラインを見極めることが必要であることを示唆している。
さらに嗅覚には、記憶と結びついているという非常に特徴的な性質がある。特定の香りをかいだ時に関連する記憶が呼び起こされることがあり、例えば粘土の匂いをかぐと、幼少期の記憶が思い起こされるといったようなものだ。フランスの小説家マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」という小説の中で、主人公がマドレーヌの焼ける香りをかいだ途端に幼少期の記憶をよみがえらせるというシーンから「プルースト現象」と呼ばれている。
これをマーケティングに活用した事例もある。米ミシガン大のA. クリシュナ教授によると、例えばウェスティンホテルでは、宿泊客が持ち帰ることのできるボールペンに香りを付けている。帰宅してペンを使った時にその香りによりホテルでの楽しい記憶を思い出してもらうことを意図しているそうだ。
嗅覚と記憶が結びついているのは、原始時代に私たちの祖先が生き残るすべとなっていたからだと考えられている。例えば木の実を手にした時に、これは毒ではないか、腐っていないかというのを判断するのに香りや臭いが判断基準となっていた。危険な臭いから過去の経験を素早く思い出さなければ生命を落としかねないため、嗅覚と記憶が強い結びつきを持つようになった。
◆パッケージで味わいも変わる
味覚は、舌だけで評価するのではない。食べ物の「おいしさ」は、視覚や嗅覚、触覚などが総合的に影響している。異なる感覚が相互に影響しあうこうした現象は「クロスモダル対応」と呼ばれる。
-e1661739802255.jpg)
(外川准教授提供)
味覚に関しては膨大な数の研究が行われている。一例を挙げると、同じヨーグルトを丸いパッケージと四角いパッケージに入れた時、四角いパッケージのものを食べた人たちの方が「風味が強い」という評価をしたという実験がある。このほか、ポテトチップスを食べる時にヘッドホンを着け、パリパリとそしゃくする音を聞こえなくしたところ、「フレッシュさ(新鮮度)」を感じにくくなったという研究もある。こうした結果からも、視覚や聴覚が味覚に影響していることが分かる。
日本では「ぷりぷりエビ」とか「ふわとろケーキ」など、食感を連想させるような擬音語、擬態語が食品名に使われている。未検証の分野だが、例えば店頭など、実際にそしゃく音を聞かせることが難しい状況でも、こうした音を連想させるネームを用いることで、おいしさを訴求することも可能かもしれない。
◆手にした物が印象を変える
続いて触覚について。私たちは日常生活を送りながら、何かしらの物を持ったり触れたりしている。この時の温度や重さ、硬さのほか、「ざらざら」「つるつる」といった触感が、無意識のうちに全然関係ない物事の判断に影響している。ホットコーヒーとアイスコーヒーのカップを持った人が、一緒にいた相手の印象を評価すると、ホットコーヒーを手にしていた人の方が相手を「温かい人」「優しい人」と評価する傾向がある。
「身体化認知理論」と言って、身体的な経験は物事の判断に影響を及ぼすことが分かっている。多くの人が幼少期に、抽象的な概念を理解するのに「温かい人」といった感覚的な言葉を使ったり、隠喩を使ったりして学習していることが背景にあると考えられている。
私自身が関わった共同研究では、電子辞書のパンフレットの用紙を硬いものと柔らかいものに印刷して消費者に渡したところ、硬いパンフレットを手にした人たちの方が、電子辞書が高品質なものだろうという印象を受けていた。「手堅い」「堅実」といった言葉があるように、硬さが信頼性に結びついたのではないかと推論している。
◆若者は「紙」を特別視?
最後に、感覚マーケティングを今後どう発展させていくか、私自身が携わっている研究を紹介させてもらいたい。
ある時、私のゼミで教えている大学生のスマートフォン画面を見せてもらう機会があった。未読のEメールが5000通以上あり、LINEのメッセージも300件以上未読のままだったことにびっくりした。他の学生に尋ねたところ、程度の差はあるにせよ、これは決して珍しいことではないらしい。店舗や営利サービスから不特定多数に発信される膨大なメッセージが、毎日のようにスマートフォンに届く。それらのほとんどは、「スルー」するか、専用のアプリでまとめて削除してしまうという声もあった。若い世代に単にメールを送っても、読んでもらうことすら難しい、というのがよく分かった。
早稲田大の恩藏直人教授をリーダーとする研究チームは、消費財を扱う国内企業と共同で、研究実験を行った。企業に登録している会員向けに、紙とメールのクーポン券を様々に組み合わせて送った。すると、紙を受け取った人たちは、メールのみ受け取った人たちに比べて、クーポンの使用率が圧倒的に高かった。私もこの研究チームに参画しているが、予想をはるかに上回る違いに驚かされた。
後日アンケート調査を行ってみると、紙とメールがもたらす心理的影響の違いも見えてきた。特に若年層は、日ごろから紙のクーポンを受け取る機会が少ない。そのため、突如、紙のクーポンをもらうと特別な喜びを感じるようである。別の実験では、企業への愛着をもった人たちには、特に、紙のコミュニケーションが重要であるという示唆も得られている。
これらの研究結果を踏まえると、旧来、効果的とされてきた顧客とのコミュニケーション対応も大幅に見直す必要がでてきている。「感覚」というキーワードを手がかりにしながら、デジタルとアナログの理想的な組み合わせを考えることが、今後重要になるだろう。
◇
上智大経済学部准教授-e1660551643395.jpg)
外川拓(とがわ・たく) 上智大経済学部准教授
早稲田大商学学術院助手、千葉商科大専任講師、米オハイオ州立大客員研究員などを経て、2020年から現職。専門はマーケティング論、消費者行動論。主な著書に「消費者意思決定の構造」(千倉書房)など。1985年生まれ。